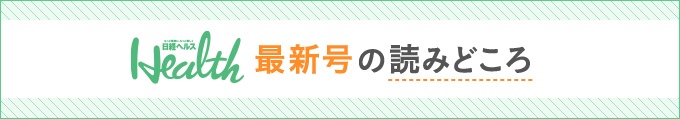開脚や前屈の書籍が話題になり、「体を柔らかくしたい!」という人も多いだろう。実は、体を柔らかくするには、肩関節と股関節を同時に動かす「動的ストレッチ」が効率的。3分でたちまち体が柔らかくなるテクニックを教えます。
「開脚をして股関節だけを柔らかくしようと頑張るより、股関節と肩関節を一緒に動かすストレッチを行うほうが、抜群に体は柔らかくなる」というのは、パーソナルトレーナーの小林邦之さん。
肩関節と股関節は連動している。例えば、歩行時。大またで歩こうとすると、腕を大きく後ろに引かないと難しい。写真のように、左手をぐーっと上げると自然と右足が浮いてくる。そんな肩関節と股関節の連動を生かした「柔軟教室」でぜひ体の柔らかさを手に入れて。